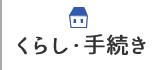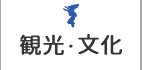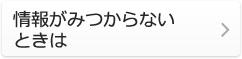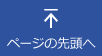「がんばれ橋 -空襲の相生橋-」
最終更新日:2016年4月1日
徳島市佐古二番町 洲崎 忠雄
「あら、お魚がいっぱい泳いでいる」橋の欄干から身を乗り出したお茶目な姉と、私に抱かれた幼い弟は、目を輝かせて川面を見つめている。夕暮れの相生(あいおい)橋、佐古川が静かなたたずまいを見せるこの界隈(かいわい)は、孫達の格好の散歩道でもある。
傾きかけた夕日が川筋にビルの長い影を落とし、台所の窓から夕餉(げ)の支度を急ぐ主婦の姿を垣間見ることができるが、阿波の夕凪(ゆうなぎ)の時刻にしては、珍しく川風が心地よく吹き抜け、全身が涼しい。私はここに立つと、辺りを見回し、―平穏だなぁ、静かだなぁ―と安堵(あんど)の胸を撫で下ろす。仰げば茂助が原の樹林の上を、数羽の烏(からす)が悠々と、ゆっくりと輪を描いて飛んでいる。
「あの事は夢だったのか、幻だったのだろうか」、そう自分の記憶に疑念を抱くほど、歳月は全ての出来事を押し流してしまった。あれからもう五〇年の世界であるとはいえ時折何かのはずみで、突然風化の扉が開かれてしまうと、バネ仕掛けのように走馬灯が回転し、「徳島空襲の舞台」へ引き戻されてしまう。
昭和二十年七月四日未明、B29の編隊が暗夜の中空に浮き上がり、激しい絨緞(じゅうたん)爆撃を開始するのである。地を揺さぶる爆発音が一瞬にして家族を引き裂き、寝込んでいた祖父と学童の私は不覚にも逃げ遅れてしまった。
「ドドーン、ドカーン」身震いするような爆裂音、彼方から恐怖を伴ってひたひたと押し寄せて来る猛火の足音、そこかしこの家屋が燃え落ちる大喧噪(けんそう)、すでに頭の中は真っ白になり、心ここに有らずだった。母達が逃れて行った道筋は、炎と煙が渦巻き、足の踏み場さえなかった。人びとは本能的に火の手の回っていない闇に逃げ込む。走りに走って、石垣の上からよどんだ佐古川へ飛び込んだ。水を蹴立てながら、何気なしに上空を見上げると、爆撃機が折しも南進中、地上の火の手が金属性の機体を不気味に映し出していた。やっとの思いで相生橋へ来た。
祖父が抱えてきた薄い夏布団を二人ですっぽり被り、水中に身を潜めた。だが、そのささやかな安らぎも、平穏な時間もそう長くは続かなかった。川添いの家屋があっという間に火を吹き、炎と火勢が一挙に加わって燃え盛り、燃え殻(がら)が音とともに水面へ落ち出した。その頃から煙に巻かれるという怖い現象も起こりだした。あり合わせの手拭を川水に浸し、しっかりと口鼻にあてた。それでも猛火と猛煙は容赦なく迫ってきた。駄目かも知れない。火炎地獄の釜の底で泣きわめき、苦しみ、のたうち、途方に暮れている老若男女の姿-。そんな地獄変を見たことがあった。
「がんばるんだ。負けてはいけない」そんな時、声を振りしぼった祖父の声が、頭の上から聞こえて来た。うつろな私にこの叱咤(しった)は大きな勇気を与えてくれた。いかついた大きな手が、私のシャツの背中を何回も、何回も擦ってくれた。それからの長い時間、祖父が何を思い、何を願って過ごしたのか、今となってはもう知るすべはない。
時々刻々、たたみかける火災の流れが、次第しだいに、いつの間にか落ち着きを取り戻し、濃い煙も大騒音も少しずつ遠ざかって行った。払暁(ふつぎょう)、残煙のただよう橋の上に恐る恐る這い出した。二人は見渡す限りの焼野が原、瓦礫(がれき)と化した町並みをあ然として眺めた。「あの佐古の町はどこへ行ってしまったのか」手のつけようもない焼け跡、くすぶる残骸と焦げるくさみ、見渡す電柱さえ、半ば焼け崩れ、電線が無残に垂れ下がっていた。
少し遅れて石垣を這い上がってきた防空ずきん、もんぺ姿の母娘があった。「よかった。よかった。あれで助かった」橋の真ん中あたり、焼夷弾の大きな落下跡を指さして喜び合っていた。
やがて焼野が原の地平線に、それまで見たこともない大きな真っ赤な太陽が昇ってきた。
「もう帰ろうよ。暗くなったから」「うん、うん、帰ろうか」夕焼けの中、私と孫達は家路をたどり始めた。
橋の上にたって、橋の下の昔を偲ぶ。いつかこの幼子(おさなご)達が成長し、物心がついた時、「空襲下の相生橋」のことを話してやりたいと思っている。
川添いのたたずまいが移ろい、住民が変わろうと、佐古川の流れは止まることはない。
「がんばるんだ。……」私が五〇年間、大切に守ってきたこの言葉が、果たして五世代を経たこの玄孫達に、どのように伝わるのだろうか。
空襲の よすが映して 川流る
このページに対する連絡先
総務課 文書担当
電話:088-621-5017
FAX:088-654-2116
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。