更新日:2025年8月15日
子ども・子育て支援新制度の対象となる教育・保育施設等を利用する場合は、保育料の支払いが必要となります。
保育料は、国が定める額を上限として、世帯の所得や認定区分、子どもの年齢ごとに、子どもの保護者が居住する市町村が定めることとされています。
保育料以外の利用者負担は、副食費(3歳児から5歳児)、延長保育、一時預かり、その他の実費徴収、上乗せ徴収などがあります。これらの費用は、施設ごとに定められていますので(市立の幼稚園・保育所・認定こども園は除く)、詳しくは利用施設にお問い合わせください。
| 階層区分 | 3号 | ||
| 0歳・1歳・2歳 | |||
| 標準時間 | 短時間 | ||
| 生活保護世帯 | A | 0円 | 0円 |
|---|---|---|---|
| 市民税非課税世帯 | B | 0円 | 0円 |
| 市民税が均等割のみの世帯(所得割非課税) | C | 16,000円 (8,000円) |
15,700円 (7,850円) |
| 市民税所得割課税額 48,599円以下の世帯 | D1 | 19,000円 (9,500円) |
18,600円 (9,300円) |
| 市民税所得割課税額 57,699円以下の世帯 | D2 | 23,500円 (11,750円) |
23,100円 (11,550円) |
| 市民税所得割課税額 72,999円以下の世帯 | D3 | 23,500円 (11,750円) |
23,100円 (11,550円) |
| 市民税所得割課税額 77,100円以下の世帯 | D4 | 29,500円 (14,750円) |
28,900円 (14,450円) |
| 市民税所得割課税額 96,999円以下の世帯 | D5 | 29,500円 (14,750円) |
28,900円 (14,450円) |
| 市民税所得割課税額 132,999円以下の世帯 | D6 | 38,000円 (19,000円) |
37,300円 (18,650円) |
| 市民税所得割課税額 168,999円以下の世帯 | D7 | 44,500円 (22,250円) |
43,700円 (21,850円) |
| 市民税所得割課税額 300,999円以下の世帯 | D8 | 56,000円 (28,000円) |
55,000円 (27,500円) |
| 市民税所得割課税額 301,000円以上の世帯 | D9 | 59,000円 (29,500円) |
57,900円 (28,950円) |
| 階層区分 | 3号 | ||
| 0・1・2歳 | |||
| 標準時間 | 短時間 | ||
| 生活保護世帯 | A | 0円 | 0円 |
|---|---|---|---|
| 市民税非課税世帯 | B | 0円 | 0円 |
| 市民税が均等割のみの世帯(所得割非課税) | C | 0円 | 0円 |
| 市民税所得割課税額 48,599円以下の世帯 | D1 | 0円 | 0円 |
| 市民税所得割課税額 57,699円以下の世帯 | D2 | 0円 | 0円 |
| 市民税所得割課税額 72,999円以下の世帯 | D3 | 0円 | 0円 |
| 市民税所得割課税額 77,100円以下の世帯 | D4 | 0円 | 0円 |
| 市民税所得割課税額 96,999円以下の世帯 | D5 | 0円 | 0円 |
| 市民税所得割課税額 132,999円以下の世帯 | D6 | 0円 | 0円 |
| 市民税所得割課税額 168,999円以下の世帯 | D7 | 0円 | 0円 |
| 市民税所得割課税額 300,999円以下の世帯 | D8 | 56,000円 (28,000円) |
55,000円 (27,500円) |
| 市民税所得割課税額 301,000円以上の世帯 | D9 | 59,000円 (29,500円) |
57,900円 (28,950円) |
世帯に2人以上の子どもがいる多子世帯については、次のとおり、第2子の保育料が半額、第3子以降の保育料が無料となる負担軽減措置があります。
教育・保育の無償化により3歳児から5歳児の保育料は無償となりますが、給食の材料にかかる費用(副食費)については保護者の方の負担となります。0歳児から2歳児の副食費分については保育料に含まれています。
徳島市立保育所・認定こども園の副食費は、次のとおりです。
認定区分 |
金額 | |
|---|---|---|
| 1号認定 | 3,500円 | |
| 2号認定 | 4,500円 | |
| 免除額 | 世帯状況 | |
|---|---|---|
全額 |
年収360万円未満相当(市町村民税所得割課税額が57,699円以下)の世帯の子ども |
|
| 第1子、第2子が就学前児童であり、かつ、幼稚園・認可保育施設・企業主導型保育施設等を利用している場合における第3子以降の子ども | ||
一部 |
上記以外の保護者が現に養育している子どもが3人以上いる世帯における第3子以降の子ども | |
第1子が満18歳未満の第2子のうち、市町村民税所得割額211,200円以下の世帯における1号認定子ども |
||
第1子が満18歳未満の第2子のうち、市町村民税所得割額168,999円以下の世帯における2号認定子ども(注釈2) |
||
保育料及び副食費は、保護者の市区町村民税所得割額の合算により決定します。
(ただし、世帯の生計の中心が祖父母等である場合(=保護者が祖父母等の税法上の扶養となっている場合 等)には、祖父母等の税額で決定することがあります。)
保育料の算定対象となる市区町村民税の年度については、次のとおりです。
所得税や市区町村民税に係る所得申告が未申告などの理由により、市区町村民税額が判断できない場合、保育料は「仮保育料」により決定します。
なお、仮保育料で決定した方は、所得申告等をしていただくことで年度内の保育料の再算定(過年度分を除く)を行いますので、担当課までお問い合わせください。
次の世帯状況に当てはまる方は、申請書と併せて次の必要書類を提出してください。
| 世帯状況 | 必要書類 |
|---|---|
ひとり親世帯 |
次のいずれか1つ
|
在宅障害児(者)のいる世帯
|
交付を受けている手帳等の写し |
| 申請児童の小学校就学前の兄弟が、市立幼稚園以外の幼稚園等を利用している世帯 | 在園証明書 など |
その他の世帯
|
要保護者等の判定に必要な書類 |
保育料及び副食費のお支払いは、原則として口座振替でお願いします。
口座振替の手続きは、利用施設が決定した後、「口座振替依頼書、預貯金通帳とその届出印鑑」をお持ちの上で、次の金融機関でお願いします。
阿波銀行・四国銀行・徳島大正銀行・徳島信用金庫・伊予銀行・三菱UFJ銀行・みずほ銀行・百十四銀行・高知銀行・愛媛銀行・香川銀行・四国労働金庫・徳島市農協・徳島県信用農業協同組合連合会・ゆうちょ銀行、郵便局の各店舗
保育料等については、法令の規定により、国が定める額を上限として所得に応じた公平な負担を保護者の皆さまにお願いしており、各市町村における保育実施に要する費用については、保護者の皆さまからの保育料等のほかに、保護者以外の方も含めた皆さまからお預かりした税金を財源として、国が2分の1、県・市町村が4分の1ずつ負担しています。
仮に年度を遡って保育料等を還付するとした場合には、国・県からの追加の費用負担は行われず、還付に必要な額は、保護者以外の方も含めた市民の皆さまからの税金のみによる負担とせざるを得なくなるため、公平な負担の観点から、年度を遡っての保育料等の還付は行っておりません。
保育料の公平な負担を図るため、上記の取扱いに関しまして御理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
新制度では、11時間までの利用が可能な「保育標準時間」と、8時間までの利用が可能な「保育短時間」の2区分に分けて保育の必要性の認定を行うこととされています。
いずれの区分であっても、通常の保育時間を超える「延長保育」を利用することが可能(注:延長保育実施施設のみ)ですが、利用者負担については区分によって違いがあります。
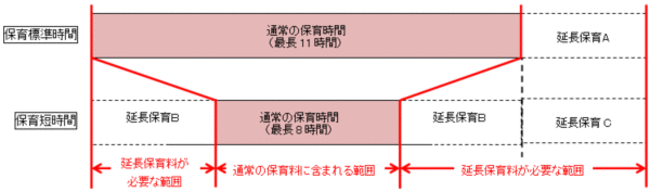
| 延長区分 | 概要 | 利用料 |
|---|---|---|
| 延長保育A | 保育標準時間に係る保育時間を超えて 利用するための延長保育 |
月額利用:2,000円/月 随時利用:300円/日 |
| 延長保育B | 保育短時間の子どもが保育標準時間と 同じ保育時間を利用するための延長保育 |
随時利用:200円/日 |
| 延長保育C | 保育短時間の子どもが保育標準時間に係る 保育時間を超えて利用するための延長保育 |
随時利用:300円/日 |
市立幼稚園では、通常の教育時間終了後に、保護者の就労などの都合により引き続き保育が必要な場合は、一時預かり保育を提供しています。利用時間や利用量は次のとおりです。
| 実施日 | 実施場所 | 区分 | 利用時間 | 利用料 |
|---|---|---|---|---|
| 平日午後 | 各園 | 午後保育日 | 14時30分から16時 | 200円/日 |
| 午前保育日 | 12時から16時 | 400円/日 | ||
| 長期休業中 (夏・冬・春休み) |
夏休み:拠点園 冬・春休み:各園 |
全日利用 | 8時30分から16時 | 500円/日 |
| 午前利用 | 8時30分から12時30分 | 400円/日 | ||
| 午後利用 | 12時から16時 | 400円/日 |
1号認定児童の平日の通常利用時間終了後や長期休業時について、特定の要件を満たす場合に一時預かり保育を提供しています。利用時間や利用料金は次のとおりです。
| 通 常 日 | 午後1時31分から午後4時まで | 500円 | |
|---|---|---|---|
| 長期休業日 | 全日 |
午前8時30分から午後4時まで | 1,000円 |
| 長期休業日 | 午前 | 午前8時30分から午後12時30分まで | 400円 |
| 長期休業日 | 午後 | 午後12時30分から午後4時まで | 600円 |
その他必要となる利用者負担としては、文房具などの教材購入費、遠足などの行事参加費、スクールバス代、PTA会費などがありますが、徴収する項目や金額は施設により異なりますので、詳しくは各施設へお問い合わせください。
保育料等に関しては、次の担当課へお問い合わせください。
| お問い合わせの内容 | 担当課 | 電話番号 |
|---|---|---|
|
子ども保育課 入所・入園係 | 電話:088-621-5193 |
|
子ども政策課 | 電話:088-621-5240 |
子ども保育課
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話:088-621-5191・5193・5195・5292
ファクス:088-621-5036