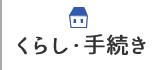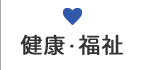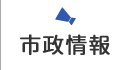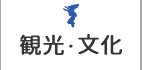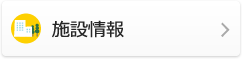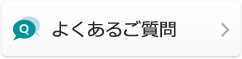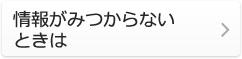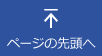新基準原付(新しい第一種原付)について
最終更新日:2025年11月19日
第一種原動機付自転車(免許区分上の「原付」)の基準が改正
従来、「エンジンの総排気量が50cc以下」とされてきた第一種原動機付自転車(免許区分上の「原付」)の基準が、この度改正されました。(設計構造や保安基準を定める「道路運送車両法」関係法令が令和6年11月13日及び令和7年2月28日、運転免許区分に関係する「道路交通法」関係法令と軽自動車税種別割の税額を定める「地方税法」の改正規定が令和7年4月1日に施行されています。)
新しい第一種原付の基準は、次のとおりです。なお、電動バイクの基準は従来と同じのままです。
1 エンジンの総排気量が50ccを超えて125cc以下の場合で、最高出力が4kW(約5.4馬力)以下であること。
2 エンジンの最高出力を上げる不正改造を防止・抑制する措置が取られていること。
3 上記2つの基準を満たしていることが、国土交通大臣による型式認定により確認できること(主要メーカーの量販車の場合)。または、「公益財団法人 日本自動車輸送技術協会 昭島研究室(JATA。東京都昭島市)」に最高出力確認申請をして上記2つの基準を満たしていることが確認されたことを示す「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」の交付を受け、エンジンブロックに「最高出力確認済シール」が貼り付けられていること(少数生産車または個人改造車の場合)。
なぜ「新基準」が必要になったか
環境美化や温室効果ガスの排出抑制が取り沙汰される昨今、バイクの排出ガス規制も次第に強化されています。
令和7年11月時点で最新のバイク排出ガス規制である「令和2年排出ガス規制」は、世界各国でも特に環境性能に厳しいと言われるヨーロッパの基準に準じており、従来型の小さな50cc原付でこの基準を満たしつつユーザーの方々に従来通りの価格で販売できるよう設計・製造することは、事実上不可能でした。
このため、従来型の50cc原付は令和7年10月末までで製造を終了し、11月以降は従来設計での50cc原付を新たに製造することが原則禁止となりました。
このままでは、普通自動車免許や原付免許で乗ることができるバイクが、高価な電動バイクや華奢な電動モペット(自転車型の電動バイク)などしかなくなってしまいます。
そこで、警察庁や有識者による会議や試作車による比較試験を経て、車体の重量とエンジンの出力の比率が概ね従来型の50cc原付と同等になる(その結果、最高速度も概ね同等に収まる)ように、今回の新基準が定められ、令和7年11月以降に製造して販売する第一種原付は、排気量こそ大きいものの出力は抑えられた新基準のものになったのです。
なお、電動バイクは排気ガスが出ないため、先に述べた通り、今回の新基準は関係なく従来の基準のまま(定格出力0.6kW以下)となっています。
また、50cc原付の中古車については販売や譲渡に制限はありませんので、これまでどおり売買や譲渡ができます。
新基準原付のナンバープレートと軽自動車税種別割の税額
新基準原付は、分類上は従来型の50cc原付と同じく「第一種原動機付自転車(第一種原付)」です。
このため、
〇ナンバープレートは白色のもの(ご当地プレート選択可能)
〇税額は2,000円/年
となります。
新基準原付の注意点
新基準原付の登録や運転に当たっては、次の注意点があります。
1 登録の際に追加の資料が必要になる場合がある
国土交通大臣の型式認定を受けている車種の場合、登録時に必要なものは従来と変わりません。(車台番号を確認できるもの・届出人の身分証明書・販売証明書(あれば)等)
しかし、型式認定されていない少数生産車や個人で改造した車体の場合は、次のものが追加で必要になります。
1 最高出力が4.0kW以下であることの確認済書(JATAから交付されたもの)
2 対象車両のエンジンブロックに貼り付けられた「最高出力確認済シール」の写真(エンジン番号と一緒に写っていることが望ましい)
2 交通ルールはこれまでの原付と同じ
新基準原付はあくまでも第一種原付です。このため、交通ルールはこれまでの50cc原付と同じです。このため、普通自動車免許や原付免許で運転することができるのですが、
法定最高速度は30km/h
二段階右折をするべき交差点では二段階右折しなければならない
二人乗り(タンデム)をしてはいけない
第二種原付であることを示す前部フェンダーの白フチマークと後部フェンダーの白三角マークは付けてはいけない
という基本ルールは変わりません。新基準原付に乗るときもしっかり守りましょう。
インターネット上では「新基準原付では二段階右折しなくてもいいようになる」という誤った情報が未だに散見されますが、大きな誤解です。ご注意ください。
3 新基準原付には、重い車体が多い
新基準原付は排気量が大きいことと、従来の50cc原付の代替車として急いで開発設計しなければならなかったことから、109ccから124cc程度の従来の第二種甲原付(免許区分上の小型自動二輪)の車体とエンジンを基に設計変更した、言わば「応急改造型」とでも言うべき車体が販売の先陣を切ります。
基になった車体が重いため、当面販売される車体は、軽いもので95kg、重いものは100kgを超えます。
70kgから80kg程度の従来型の50cc原付しか乗ったことがない方々には、かなり重く感じると思います。押し歩きをするときや倒れた車体を起こすときには、十分ご注意ください。
4 走り出しのときの加速は従来型の50cc原付よりも強め
製造禁止となる直前に造られていた50cc原付は、排出ガス規制の影響もあって、持続的なエンジン出力だけではなくエンジンがギア・チェーンを介してタイヤを回す瞬間的な力(トルクと言います)も弱くなっていました。
その一方、新基準原付は最高出力こそ抑えられたものの、元々の排気量が大きいためトルクについてはあまり小さくはなりませんでした。
このため、走り出しの加速力(初期加速力)や最高速度に達するまでの加速力が、従来型の50cc原付に比べて強めになっています。
従来型と同じ感覚でスロットルグリップを捻ってしまうと、思わぬロケットスタートをするかもしれません。
購入の際などに、販売店の方やバイクに詳しい方のアドバイスをしっかり聞いて、安全な発進・加速を心がけましょう。
関係先リンク集
![]() 警察庁・一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(外部サイト)
警察庁・一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(外部サイト)
お問い合わせ
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。